こんにちは。11歳と1歳、年の差きょうだいを育てるワーママです。毎日、仕事・家事・育児に追われる中で、少しずつ「お金の教育」にも目を向けるようになってきました。
というのも、小学生の上の子は「欲しい!買って!」が増え、下の子はスーパーで何かを見つけるたびに手を伸ばすように…。
「お金って、どうやって教えたらいいんだろう?」 「欲しい=すぐ買う、じゃないことをどう伝えればいい?」
そんな悩みから、少しずつわが家なりの“お金の教育”を始めてみました。
この記事では、
- いつからどうやって教える?
- 小学生・未就学児へのアプローチの違い
- おこづかいについての失敗とおこづかい制度(家計簿)の実施
- 親として気をつけていること などを、等身大でお伝えしたいと思います。
◆ お金の教育は“早すぎる”ことはない
私たちが子どもの頃、「お金の話」ってあまり家庭でされませんでしたよね? なんとなくタブーのように扱われたり、「親が管理するもの」という空気がありました。お年玉も親に渡したきり、大人になって銀行に貯金してくれていたことを知りましたが、それまで気にすることもありませんでした。
でも今は時代が変わり、現金に触れる機会も少なく、ネットで何でも買えてしまう時代。 そんな中で“お金の使い方”を学ばずに大人になることが危険だと思うようになりました。
お金の価値、限りあるものだという意識、貯める力、そして「使い方の選択肢」。 これは生活力の一部です。
だから、たとえ小さくても、子どもにお金の話をすることを恐れなくていい。 日常の中にヒントはたくさんあると感じています。
◆ 買い物を通して、1歳でも「お金」に触れられる
1歳の娘に本格的な金銭教育はまだまだ難しいですが、ちょっとした日常の会話でも「お金って大事なんだよ」という感覚を伝えられるようになりました。
たとえば、
- 「これは今日は買わないよ。お金がかかるからね」
- 「これ100円なんだって。さっきのより安いね」
といった何気ないやりとりも、小さな積み重ねだと思っています。
まだ理解はしていなくても、「欲しい=手に入るわけじゃない」と伝えていくことが、きっと将来の土台になるはず。
◆ 小学生の息子には“おこづかい制”スタート
今までは特におこづかいを渡しておらず、必要な時に少しだけ、お年玉などから渡していました。しかし、小学生高学年になると自分や友達とスーパーやコンビニでお菓子を買ったりするようになり、すぐにお金を使ってしまう癖が出てきました。渡したらあるだけ使ってしまう。その繰り返しでした。
そんな浪費家の息子のために、おこづかい制をはじめました。
月1000円でスタートします。
すぐに使い切ってしまって後悔したり、逆に貯めて買ったときの達成感を感じたり。 そうした実体験が、何よりの学びになっていると感じます。
◆ すぐに使っちゃう息子に、「おこづかい帳」も導入!
とはいえ、まだまだ「欲しい!」が先に立ってしまう息子。 おこづかいをもらったそばから使ってしまい、あとで「やっぱりこっちが欲しかった〜」と後悔することも。
そこで、今月から【おこづかい帳】を始めました。
と言っても難しいものではなく、
- 何を買ったか
- いくら使ったか
- 満足だった?後悔した? などを簡単にメモするだけのもの。
最初は「え〜めんどくさい」と言っていたけど、意外と気に入って続けてくれています(笑)
先日息子がコンビニで200円くらいのレジ横ホットスナックを買ったことを後悔していました。
「なぜ後悔したの?」と聞いたところ、「本当は別のものが欲しかったけれど、なかったから欲望のままに買ってしまった」とのこと。そして家計簿をつけると、自分のお小遣いが少なくなったことにガッカリしたよう。また、その際にレジ袋ももらっており、「袋にもお金がかかるんだよ!」と伝えたら、「知らなかった…」とさらに後悔しておりました。
このような後悔もまた勉強の一つ。家計簿をつけ始めたから分かったことかなと思います。
この先どんな結果になるか、また改めてレポートします♪
◆ 親が“お金の話”を自然にすることが大事
子どもにお金を教えるには、親自身が「お金の話=前向きなもの」と思えていることが大事だと感じます。
私は以前、どこか「お金=苦手」「節約ばかりが美徳」と思い込んでいました。
節約でお金を貯めるに専念するタイプ。どこまでも安いものを探すことを生き甲斐にしていると言ってもいいくらい。でも、それって子どもにも伝わるんですよね。回転寿司で安いのを頼むとか、子供が高い寿司を気にせず頼んでいるのを見て、ちょっと考えてなど言ってしまったり…。後で子供はどう思ったのかな?と心配になりました。
だから、
- 家計簿を一緒にのぞかせて「今月はこれくらい使ったね」
- 節約した分で「これ買えてよかったね」と共有する
- 「この買い物は高かったけど価値あったよね」と話す
そんな会話が日常の中に少しずつ増えてきました。
子どもは親の“背中”を見て育ちます。だからこそ、私も一緒に学びながら成長していこうと思っています。
◆ まとめ:お金の教育は、家庭の中の会話から
お金のことって、難しく考えすぎなくてもいい。
大事なのは、“子どもと一緒に悩みながら考えること”。
「今月使いすぎちゃったね、来月はどうする?」 「これとこれ、どっちが本当に必要かな?」
そんな日々の会話の積み重ねが、子どもにとっての「お金の感覚」を育ててくれると信じています。
まだまだわが家も試行錯誤中ですが、これからも子どもたちと一緒に、お金と上手につき合う力を育てていきたいです。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
今後も子供のお金との付き合いかたについて発信していけたらと思います!

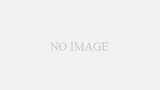
コメント