はじめに:NISAって何?NISA口座の開設
NISA(少額投資非課税制度)は、年間一定額の投資による利益が非課税になる制度です。
私は2020年、将来に向けた資産形成を意識し始め、投資未経験ながらも初めてNISA口座を開設することを決意。投資について無知の状態でネット証券会社で口座開設するのは初心者にはハードルが高く、手取り足取り教えてくれる地元の地方銀行でスタートしました。
当時の私は投資に不安があり、対面で相談できる環境を重視して地方銀行を選びました。この記事では、2020年〜2022年にかけて地方銀行でNISAを活用した実体験をベースに、私自身がメリット・デメリットを感じたことを赤裸々にお伝えします。
地方銀行でのNISA運用:具体的な流れと選択商品
NISA口座の開設手続き
地方銀行でのNISA口座開設は、正直に言って手間がかかりました。地方銀行では窓口での対応が必須。本人確認書類の提出や、必要な説明を資料や口頭でたくさん受けました。平日に仕事の休みを取って半日がかりの手続き、当時の自分には知識がないため、これが精一杯でした。
銀行での手続きが数時間、開設から実際に運用を始めるまでには、約3週間ほどかかりました。
地方銀行が勧めてくれた金融商品
購入時も半日かかりで、銀行窓口へ、担当者から紹介されたのは主に以下のような商品です:
- 国内株式を中心とした投資信託(分配型)
- 債券混合型ファンド
- 金(ゴールド)関係のファンド
- 流行りのAI、テクノロジー系のファンド
正直、自分ではどれが良いのか判断できなかったため、初年度は窓口担当者のおすすめした3つの投資信託を購入。一般NISA枠120万円を、50、50、20に分けて分散しました。初年度含め3年間360万円それぞれ毎年3銘柄ぐらいに分散投資。
運用結果:2020年〜2022年の実績
3年間での投資額合計:約360万円(一般NISA年間上限額120万円✖️3年)
2024年末時点での評価額:約500万円(税引き前、非課税のためそのまま利益に)
※私がNISAを始めたのは2020年9月コロナショックで一時的下がっている時に始めたため、2021年は利益が出る。2022年は利益減にその後の世の中の情勢よって上がり下がりを繰り返しました。
結果コロナショックの際に始めたという点、非課税という点で利益が出た結果となりました。
相場の動きと影響
- 2020年:コロナによる急落で評価額が下がる(評価額が下がったタイミングで買付)
- 2021年:世界的な金融緩和で株価回復、含み益へ
- 2022年:円安とインフレでやや乱高下するも、トータルではプラス維持
地方銀行でNISAを使うメリット
1. 対面サポートが手厚い
初心者にとって最大の安心材料は「人に相談できる」こと。運用が不安になった時、地元の銀行窓口で担当者に直接相談できたのは大きかったです。
2. 安心感と信頼感
地元で長年親しまれている銀行ということもあり、精神的な安心感がありました。資産を「顔の見える相手」に任せているという信頼も投資継続の後押しになりました。
3. 投資教育の一環になる
定期的に開催される資産形成セミナーや勉強会にも参加でき、NISAだけでなく「投資信託とは何か」といった基礎知識も学べました。
地方銀行でNISAを使うデメリット
1. 商品の選択肢が限られている
ネット証券に比べて、選べる金融商品の数が圧倒的に少ないです。信託報酬(手数料)が高めの投資信託が多いです。低コストのインデックス商品はごく一部のため、おすすめされませんでした。
2. 手数料が高い
対面サポートのコストがある分、どうしても信託報酬が高くなりがち。仮に同じ商品でも、ネット証券会社の方が手数料が安く設定されているケースが多かったです。地方銀行での投資信託の購入時手数料は平均3%程度。この手数料が投資信託の銘柄によってかなりの差があることは後に知ることに...
3. 運用の自由度が低い
例えば「もっとリスクを取って米国株に集中したい」などの希望があっても、銀行側の取扱商品ではカバーできないことが多々ありました。よって途中で乗り換えたくても、NISA口座は年単位で金融機関変更ができないため不便でした。
経験してわかった「地方銀行NISA」が向いている人・向いていない人
向いている人
- 投資初心者で、まずは仕組みから理解したい
- 何かあった時にすぐ相談したい人
- 地元の銀行と付き合いがあり、安心して任せたいと考える人
向いていない人
- 自分で商品を選びたい、自由に運用したい人
- 手数料をできるだけ抑えて長期で効率的に資産を増やしたい人
- 海外ETFや個別株投資に興味がある人
結論:最初の一歩としては「あり」、でも将来はステップアップを
私自身、地方銀行でNISAを始めたことに後悔はありません。資産形成の「入口」として非常に有益でしたし、知識ゼロでも安心して始められる環境があったのは大きかったです。
しかし、経験を積むうちに「もっと自分に合った商品を自由に選びたい」という欲が出てきたのも事実。2023年にはネット証券口座にNISA口座を移し、より低コストなインデックスファンド等で積立を継続しています。
まとめ:情報収集をして、証券口座の開設を!
2020年〜2022年の3年間、地方銀行でNISAを活用した私の結論は以下の通りです
- 地方銀行のNISAは、投資初心者にとって安心して始められる環境が整っている
- ただし、商品ラインナップやコスト面ではネット証券会社に劣る点がある
- 「投資を知る・慣れる」ためのステップとしては非常に有効
NISAはあくまで手段であって目的ではありません。自分の資産形成の目標と照らし合わせて、適切な金融機関と商品を選ぶことが重要だと、この3年間の経験から痛感しています。
私は3年間地方銀行でNISA口座を開設後、楽天証券、SBI証券とNISA口座を移しました。やはり手数料、窓口対応の手間の点からネット証券口座の方がライフスタイルに合っていると気づいたからです。
楽天証券、SBI証券では、現在手数料の少ないインデックス投資をメインで行っています。
2020年当時はネット証券の口座開設についての知識や教えてくれる教材なども少なく、銀行窓口に頼るしかありませんでした。
しかし現在は書籍、SNS等でたくさんの情報を収集できます。ネット証券口座の開設方法についても分かりやすく解説しているものもあるので、ぜひ参考にしてみてください。

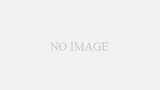
コメント